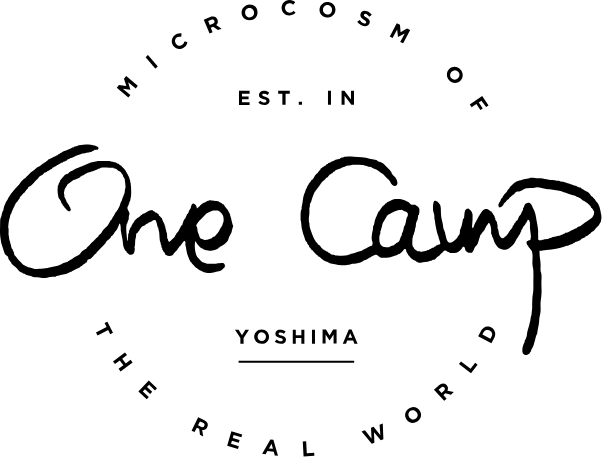One Camp日誌 - キャンプディレクターの日記
One Camp日誌 - キャンプディレクターの日記

今年は暑い。とても暑い。日焼けしたと思ったらまた日焼けする。コロナの不況を乗り切るために人を減らしたから、まだそれが尾を引いている。キャンプ場のすべての仕事を数人で回している。でも仲良しだからなんてことはない。子どもも大人も、よくわかってる人は手伝ってくれる。
余島の歴史は長いけれど、その歴史を正当に理解している人は少ないと思う。特にここ10年は伝統の良さを失わせずに変革した。その良さを口で説明できる人にはほとんど出会わない。五十嵐さんはOne Campを初めて見て「阪田さんらしい島になったよね」と言ってくれたと言う。森本さんはこの島は自由でいいよねという人に「彼がマネージャーだからだよ」と言ってくれた。よくわかっているなと思う。
かなたもゆめとも、戦友のような感じがする。立派になったなとも思う。のぶくんはあいかわらず。けいゆうはゆっくりだけど嬉しそうな顔をする。たけまくんは精悍になって。カルーナもファンファンのとこも。何も募集してないのにこんなに集まる。
キャンパーのみんなに一時間半に渡って余島の現状を話した。「公共性」がテーマだったけど、カルーナの一人が「自分はまだ参加者だけどいつか当事者に」と言っていたと聞いた。すごいことだ。カウンシルファイヤーで確信した。これまで説明した中で誰よりも本当のところをわかっているキャンパーたちだ。
ちゃんと対話せよ、と思う。余島にいて、余島が置かれた状況を説明すると、みんなさまざまな反応をする。でも率直だから、徴候的に物事を捉えることができる。多くのことはどうでもいい。言葉ですっきりすることもない。言葉にだけ振り回される人にうんざりする。でもよくわかる。だからいい。
Camp Director 阪田晃一
2024.8.31 哲学者との山旅
東山荘に務める実弟のよっちゃんが、今回は白鳥さんとガイドをしてくれた。この夏もヘタレが何人か富士登山に紛れ込んだようだ。行きのバスで教えてくれた。
今回もヘタレそうなやつが紛れ込んだ。彼の声かけを注意深く聞いていた。
「風に靡くな」
「遅れをとるな」
「しっかりと一歩一歩自分の足で歩め」
「気を抜くな」
よっちゃんは初期ギリシャの研究者だった。ソクラテス以前を扱っていた。僕は彼の富士登山への関わりが、初期ギリシャ的な観念に貫かれていると思った。
ニーチェは言った。大いなる軽蔑こそ始まりだ。ニーチェは人の意見に靡いたり、自らの意志に遅れをとったりすることを極端に嫌った。ヘタレが大嫌いだった。ニーチェも初期ギリシャの文献学者だった。
よっちゃんはその子に問うた。
君は登りたいのか?そうじゃないのか?
登れるかどうかではない。したいかどうかだ。
いやいやここに来たのか。なぜ答えない。
聖書を原文で読める彼が、東山荘という歴史ある場所で、山に人々を案内する仕事についている。僕は彼の実存が好きだ。草刈りをしたり木々の剪定も自らの意志で行なっている。
哲学を追求した者が、心からしたいことをしながら好きに暮らしている。シュタイナーも同じように、このギリシャ的な実存を愛でた。
白鳥さん、よっちゃんらは地下足袋で登る。僕も膝が痛かったので真似してみた。山を一歩一歩、静かに歩く彼らはまさに哲学者だった。そんなことを考えながら歩き終えた富士登山だった。
Camp Director 阪田晃一
2024.9.2 「善良な人々」
「善良な人」がいるとしたら、余島一豪さんかもしれない。今日久しぶりに会ってそう思った。
余島さんは変わっていなかった。もう17年ぶりで、やっぱり年はとっていたけど、昔のままの余島さんだった。僕は2006年に働き始めて、1年間は余島さんと一緒だった。
- ほれ、あの、その、それがー
余島さんはいつもそんな感じで話していた。
当時もほとんど何を言ってるかわからなかったけれど、よく覚えていた。
一瞬で余島さんの空気に触れて、余島のYMCA前史の景色が見えた気がした。
YMCAが来る前は、余島一豪さんで14代か15代目になる一族だった。
一豪さんは、余島で、余島邸で生まれた最後の長兄だ。
-家系図はないんですか?
-あったげにいうけどな、そういったものはぜんぶだましとられてしもうた。
病気が治るって言われてた金の箸やら、宮さんにもろうたお守り人形やら、ぜんぶのうなってしもうた。
一豪さんは、小学校6年生で亡くなった実父の喪主をしたそうだ。
大婆さんが病気になった時も、奥様と二人で献身的に支えたそう。
「善良な市民」がいるとしたら、余島さんのようなお二人を言うんだろう。搾取され、騙され、でも健気に目上の家族を大切にし、自分の時間とお金をかけてお世話をした。子も育てた。畑を耕し、森をきれいにし、周辺の海のこともぜんぶ知っていて、道具の手入れを怠らなかった。決してでしゃばらず、わきまえ、自分よりも他の誰かを優先した。
文字もろくに読めないから騙されたんだと、半ば哀れみを込めて奥さんが言った。
しかしその哀れみには、強い不憫さはない。それでも一生懸命生きてきたんだ。祖先に、お天道様に、人の道に逸れることは何一つしてこなかったからいいんだ。
そんな「自己信頼」に溢れていた。
古い話だからよくわからないけれど、余島には大地主がいて、さらにいくつかの持ち主がいて、余島さんは果樹園を営みながら暮らしていた。ある時、大型の資本がやってきて、その土地が完全に「誰かのもの」になってしまった。その後YMCAが入ってきて、今井先生らがやってきて、余島がキャンプ場になった。
しばらくして、余島さんが持っている土地も地主さんに売られた。
一豪さんも自分の歳の頃がいい時に働きたかったけれど、それは叔父に譲った。
でも数年間でも、自分が生まれた場所で働けたことがよかったよと奥様が言った。
僕たちはYMCA以後の歴史しか知らない。しかし余島はずっとそこにあり続けた。少なくとも15代に渡って余島を守ってきた人たちがいることを、僕たちは決して忘れてはならない。
一代は30年と数えるらしい。450年もの間、余島で暮らした人々のことを思う。
「善良な国民」に登録される前の「善良な人々」が、幾人も存在しただろう。YMCAはそんな人々に、多大な、決定的な影響を与えた。だからこの歴史の転換期に、組織の人間がせめて誠意を持って説明すべきだろう。
説明したって何にもならない。それはその通りだ。でもそう言う問題じゃない。人々の営みは記憶に支えられている。僕は今日、とても重い、重くて重くて背負いきれない歴史をまた一つ背負った。それは余島のYMCA前史だ。余島のYMCA史はたった75年。余島さんの歴史は450年。その重みがわからなくなったら、その文明はいずれ終わるしかない。
Camp Director 阪田晃一
2024.9.13 余剰したエネルギーをどこで使えばいいのか、バタイユの問いの重要性
久しぶりに声を聞いた。相変わらずでこちらも嬉しくなった。
バタイユは『呪われた部分』で<消費>に注目した。この宇宙の生命は余剰した、もしくは過剰なエネルギーの浪費で成り立っていて、そのことを無視した結果戦争が起きたとしている。
バタイユは「生産的消費」が称揚される社会がダメだと言った。生産的消費とは、生産と保存を目的とする、今や一般的なエネルギーの使い方だ。資本主義の原理だとしている。ではそれではなぜダメなのか?それはもともと僕たちは太陽に憧れていたからだ。太陽はすべてに「降りそそぐ」という本質を持つ(本質を人間が与える前に太陽は燃えている!)。つまり与え続ける。誰からも貰わないのに与え続ける「非生産的消費」。その凄さに人々は感染した。
だから人類はずっと、正確には持続可能な文明(のようなもの)を有していた人々は「非生産的消費」を称揚してきた。手段的に、道具的に、「こうすればこうなるから」と(せっかく)余剰させたエネルギーを使うことを呪ってきたのだ。だからバタイユの本の題名は『呪われた部分』なのだ。
※でもバタイユは、今はその二項図式が逆転してしまっているという意味で、現代の人々が呪っている部分こそ「至高」なのだと言った。
若者にはエネルギーがある。原生自然もエネルギーに満ち溢れている。僕たちは万物の「余剰」を贈与しあって生きている。では若者の本質はなんだ。それは太陽のように自分のエネルギーを「ただ使い続けること」。打算的な消費ではなく、目的的な消費。余島はそれを可能している場所だと言える。74年間、若者がただ力を使い込めるところ。そんな場所だ。
若者はいつも本気だ。どんなときでも、ただその力を使い、すべてを「非生産的消費」に充てている。バタイユや太古の人々が愛でた、英雄なのだ。初期ギリシャの人々が知っていたように、英雄は自らの命を顧みず、信ずるままに突き進む人。ただ使え。そうだと思ったらぜんぶ使え。出し惜しみするな。若い人にはそう言い続けてきた。特にコロナ以降は良く言うようになった。
若者よ。生産的消費に自らを費やされるとしても厭わず、それでも使え。ただ使い続けろ。そのエネルギーをぜんぶ使え。なにも案ずることはない。お前の中で燃えているのは太陽だからだ。尽きることのないエネルギーがお前の中で燃えている。それが一緒に見た炎の中で輝いていた光だ。
バタイユの、自由で柔軟な生態学的思考に驚愕しつつ、若者の頑張っている姿に僕も力をもらった。そして改めて思った。やってる感社会に『呪われた部分』とはよく言い当てたものだ。バタイユもサルトルもフランス人だった。理性革命に燃えた人々が持つ責任感から来る動機なのだろう。
バタイユの『呪われた部分』は「全般経済学試論」として書かれた。その強い動機はどこからきたのか。<消費>の仕方を間違うことはできない。なぜなら人間はもともとただエネルギーを使うために生きているからだ。生産と保存がエネルギーを溜め込みすぎて、最大限に無駄な浪費=大量な殺人を仕立て上げた。それがヒロシマの原爆だ。だから僕たちは、そう断言するバタイユを読まなければならないのだ。
Camp Director 阪田晃一